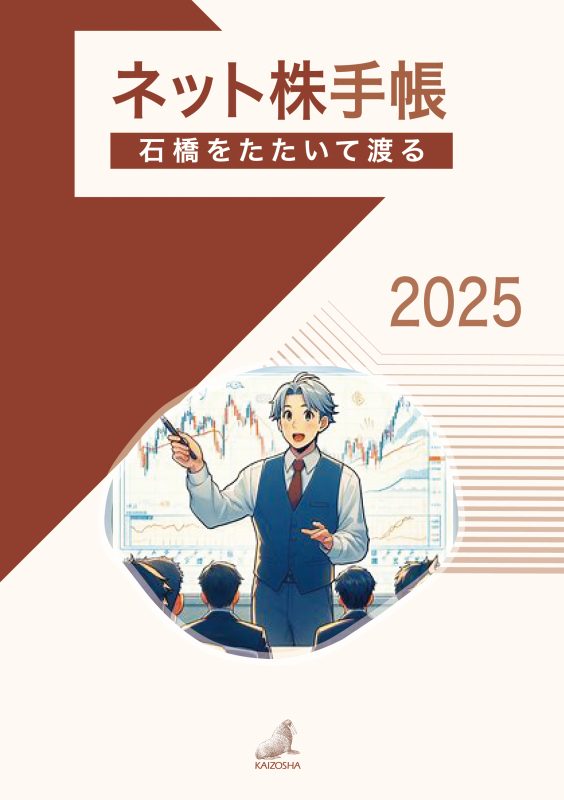つれづれ
2025年の株価展望―4万5000円台も視野に
2024年の大納会(12月30日)の日経平均終値は3万9894円で、前年の大納会より6430円(約19%)も上昇しただけでなく、過去最高額だったバブル期の1989年大納会の3万8915円も上回りました。2025年の東京証券取引所や経済見通しはどうなのか、『ネット株手帳 2025』の著者、三橋規宏氏(日本経済新聞社元論説副主幹)に聞きました。
▽経済成長、日米金利、主要国政府の経済運営は…
世界は大きな転換期を迎えているようです。欧米先進国では民主主義の根幹を支える寛容な精神が片隅に追いやられ、分断の嵐が吹き荒れています。中国やロシアのような国家では武力行使による「領土拡大」を辞さずの姿勢が目立つのが気になります。また、AI技術が急速な発展を遂げる一方、SNS経由で様々な偽情報が拡散され、政策決定や企業活動にまで悪影響を及ぼしています。
株価や為替に影響を与える経済的な要因については原因分析、予想がかなり可能です。大きな要因としては、①世界の景気がどうなるか、②経済活動に影響を与える政策金利の動向、③主要国政府の経済運営、政策当局者の発言――があります。ただ、株価は国際情勢の変化、技術進歩、気候変動による異常気象や災害など森羅万象の変化を反映することから、不確実な要因に左右されることがあることも頭の片隅に置いてください。
【世界経済は3%成長が可能】 『ネット株手帳』の9ページ「IMF世界経済の見通し」をご覧ください。新興国を含めた世界全体では3%台の経済成長が維持できそうです。米国は少しブレーキがかかりそうですが、日本とユーロ圏は順調な回復軌道をたどりそうです。中国経済は気になりますが、戦火の拡大や大災害などが起きなければ、世界経済は無難な1年になりそうです。
【日米金利差は縮小の方向】 日米中央銀行による政策金利の動向が株価に大きな影響を与えます。日銀の政策決定会合は1月23~24日、米国のFRB(米連邦準備制度理事会)の政策決定会合(FOMC=連邦公開市場委員会)は同28~29日に開催されます(『ネット株手帳』10ページ「日米の金融政策会合スケジュール」参照)。
日銀は昨年3月の政策決定会合で、マイナス0.1%としてきた政策金利(無担保コール翌日物レート)を0~0.1%に引き上げました。日銀の政策金利引上げは約17年ぶり、マイナス金利是正は約8年ぶりでした。4カ月後の7月末の決定会合ではさらに政策金利を0.25%まで引き上げましたが、株価の大幅下落を招き「植田ショック」と言われました。今年1月末の決定会合で、日銀がさらに0.25%の引き上げに踏み切るかどうかに市場の関心が集まっています。今回見送ったとしても、円安への懸念から3月の政策決定会合では踏み切らざるをえないでしょう。日銀は政策金利の上限を1%程度としているようで、その後年内に2回、それぞれ0.25%の引き上げに動くものとみられます。
一方、FRBはインフレ対策から22年3月に政策金利(フェデラルファンドレート)の引き上げに踏み切りました。その後FOMCが開かれるたびに金利を引き上げ、23年3月には5.25~5.50%まで上昇しました。金利水準がここまで高くなると、企業の設備投資などに悪影響を与えかねません。FRBは24年9月に0.5%引き下げたのを皮切りに、10月と12月もそれぞれ0.25%引き下げ、金利水準は4.25~4.50%まで低下しました。今年はさらに2回、引き下げる見込みです。1月下旬のFOMCで0.25%引き下げに踏み切るかどうかが焦点です。FRBは景気に対し中立的な金利水準を約3%と見ているようです。1月末の政策会合で日本が0.25%引き上げ、米国が逆に0.25%引き下げれば、円安にかなりのブレーキが働くでしょう。
【トランプ2.0の保護主義拡大が懸念】 1月20日にトランプ氏が2期目の米大統領に就任(トランプ2.0)します。戦前の大恐慌時代、アメリカは40%前後の高い関税の壁を築き、それが世界経済のブロック化を招き、第二次世界大戦につながった苦い経験があります。この反省もあり、戦後の歴代米大統領は関税引き下げ、自由貿易推進の旗手として世界経済の発展に貢献してきました。ところが、「アメリカファースト」を掲げ、“保護貿易の権化”のような大統領の2期目が始まります。「トランプ2.0」は中国を初め、貿易赤字国に対し大幅な関税引き上げを迫るものと見られ、世界各国の株価に大きな影響を与えそうです。もっとも、「トランプ2.0」は国内インフレを加速させ、米国企業の国際競争力の低下を招き、経済を弱体化させてしまう危険もはらんでいます。そうなれば、アメリカの有権者が反旗を翻す可能性もあります。まずは「トランプ2.0」の展開を注意深く見守る必要があります。
▽24年の最高値上回り、4万5000円台に乗せるか
今年の日本の株価はどう動くでしょうか。昨年の大納会株価は3万9894円で、6430円上昇しました(24年大納会―23年大納会)。その前年(23年大納会―22年大納会)は7370円上がりました。コロナ禍後の2年間で1万3800円も上昇したことになります。「2度あることは3度ある」の楽観論に立てば、今年の株価が4万5000円台に乗せるのはそれほど無理な見方ではありません。
さらに、日経新聞が毎年元旦の紙面で掲載する主要企業の経営者20人に聞く「今年の株価見通し」によると、回答者の9割が昨24年の最高値(4万2224円、7月11日終値)を超えると答えています。また、株価予想の平均は4万4450円でした。この数年、上場企業の多くはPBR(株価純資産倍率)やPER(株価収益率)の引き上げ、株式の持ち合い廃止など財務体質の改善に取り組んでいます。外国人投資家も日本企業の将来を評価して株式購入を増やしています。昨年から始まった新NISA制度の導入で若者層の株式投資も急増しています。今年は年間5000円以上の株価上昇が見込まれると筆者は予想します。
◆『ネット株手帳 2025』の配当金記入欄への対応◆
『ネット株手帳 2025』配当金記入欄(72、73ページ)にミスがありました。ここにお詫び申し上げます。
2024年12月11日以降ご購入の方は該当ページを修正した『ネット株手帳 2025』第2版をお買い求めていただいています。それ以前にご購入の方は弊社ホームページの「お問い合わせ」にて、「お問い合わせの種類」を「出版物について」とし、本文に「ネット株手帳送付」と入れ、ご住所・名前を記入してお送りください。修正した『ネット株手帳2025』(2版)を郵送します。または、本文に「差し替え」と入れて送信いただけましたら、差し替えの2ページ分のPDFをメールにてお送り致します。